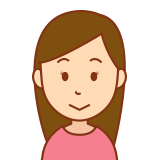
リーディングで高得点を取るためには精読が重要とは聞いたけど、
・精読をするべき理由は?
・精読の具体的なやり方と練習方法は?
・精読の練習におすすめの教材は?
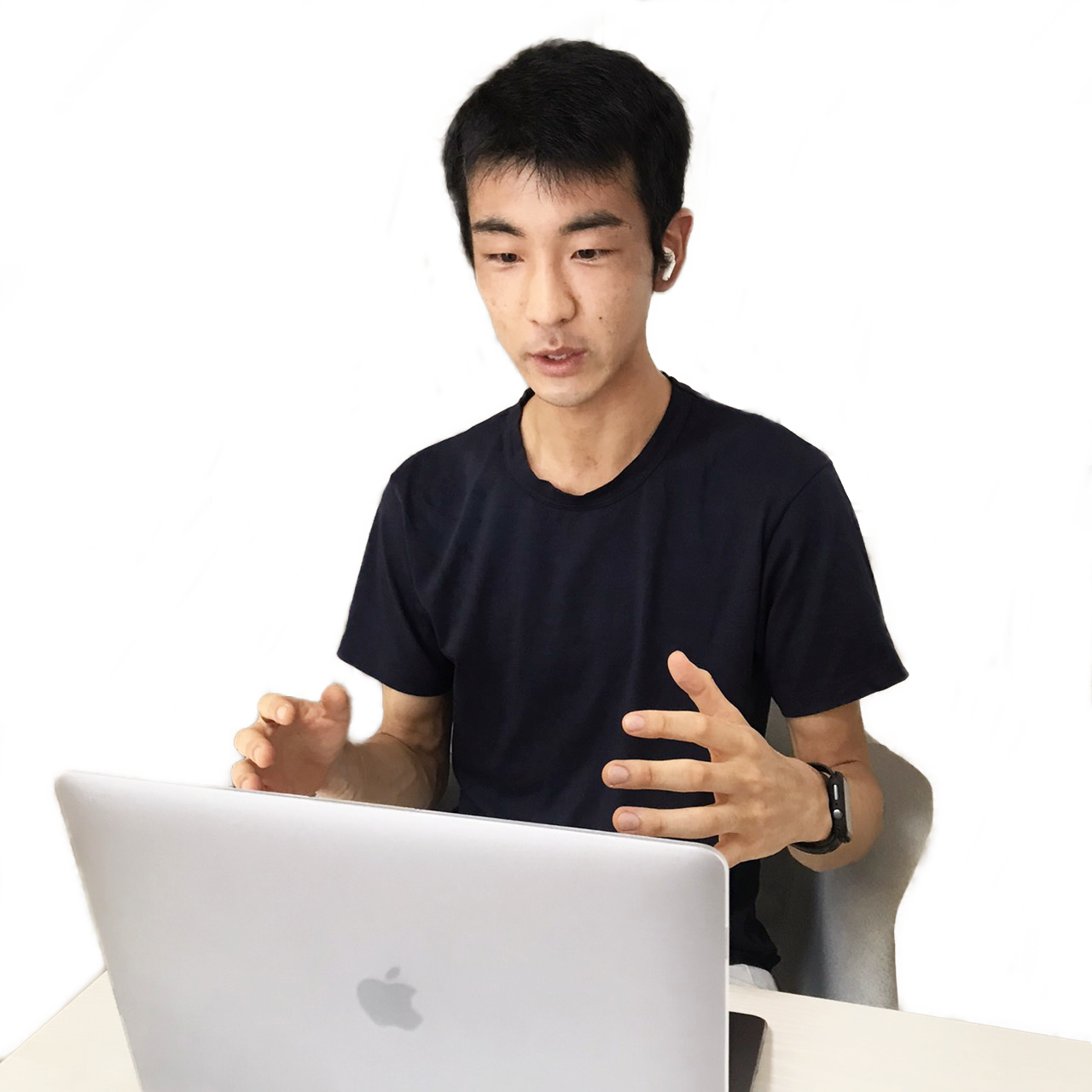
このブログを運営しています稲垣達也(@T_Inagaki_GC)と言います。
僕は精読力を鍛え続けた結果、TOEICとTOEFLのリーディングで満点を取得しました。
本記事を最後まで読んで頂くことで、これらの疑問を解消します。
本記事では、リーディングの根幹である「精読」について、僕のこれまでの知識と経験を元に、徹底的に掘り下げていきます。
この記事を通して、「精読の重要性」とその「具体的なやり方・練習方法」が少しでも伝われば嬉しく思います。
「精読」の定義
まず、精読の話を進める前に、この記事内で用いる「精読」という言葉の定義からはじめます。
参考用に、こちらはGoogleで「精読とは」で検索した際の検索順位1位のページからの引用です。
細かいところまで、ていねいに読むこと。熟読。
精読とは – Weblio辞書
この定義でも「精読」という言葉のニュアンスは伝わりますが、これではまだ抽象度が高いように感じます。(「丁寧に読む」という程度が人によって差があるため)
そこで、この記事で用いる「精読」という言葉の意味を、僕が勝手に定義します。
僕が定義する「精読」とは、
この定義を用いることで、かなり具体度が上がりました。ただもう少し改善の余地があるように感じます。
特に後半の「明確に理解する」という部分が、人によって解釈が分かれると思います。そこで 「明確に理解する」 という部分をさらに具体的にした場合の「精読」という言葉の定義を考えます。
「精読」とは、
すなわち、その文章が「なぜそのような意味を読者に伝達するのか」を、他者に説明できる状態まで、深く文章を理解する行為のこと。
これで、かなり具体的になりました。
重要なポイントは、「他者に説明できる」という部分です。
というのも、基本的に1つの文章は、1つのメッセージを読者に伝えます。(もちろん例外はあります)そのため、その文章に含まれる全ての単語、文法を明確に理解できていれば、誰が読んでもその文章の解釈は同じになります。
すなわち、文章の意味を読んで理解ができている状態とは、文章を読んだ末に皆がたどりつく「共通の解釈」ができている状態であり、この「共通の解釈」にたどり着くための行為こそが「精読」だと考えます。
そのため、精読ができている状態とは、その「共通の解釈にたどり着くまでの過程を、他者に説明できる状態である」と定義しました。長くなりましたが、大事な部分なので丁寧に説明しました。
精読をするべき3つの理由(精読の効果)
精読の具体的なやり方を説明する前に、精読をするべき理由を確認しておきます。
①文章の意味が正しく自信を持って理解できる
精読をすることにより、文章の意味が正しく自信を持って理解できます。
特に重要なポイントは、「正しく自信を持って」という部分です。
というのも、リーディングが苦手な人のほとんどが「なんとなく意味はわかるけど、ほんとにこれであっているんだろうか」という状態で文章を読んでしまっていると思うからです。(精読に真剣に取り組む前の僕はそうでした)
そのため、文章の意味が正しく理解できず、結果的にそれらしい選択肢を選ぶことが増えるため、思うような点数が取れない可能性が高くなります。
一方、精読ができれば、リーディングの正答率が上がることはもちろん、自信を持って正解の選択肢を選べるため、次の問題にも集中しやすくなり、結果的にリーディング全体の正答率が上がる、という好循環が発生します。
②文章を読むスピードが早くなる
精読ができるようになると、文章を読むスピードが上がります。
「精読」という言葉を聞くと、文章をゆっくり丁寧に読むため「読むスピードが遅くなるのではないか」と思う方もいると思いますが、僕はむしろ文章を読むスピードが早くなると感じています。
なぜなら、精読ができれば「文章の意味を一度読んだだけで理解できる」ようになるからです。
これは何か明確な根拠があるわけではありませんが、そもそもの文章を読むスピード自体に、人による大きな差はないように思います。
ただ現実は、文章が速く読める人と、文章を読むのに時間がかかってしまう人の両方が存在します。
では、この差は何によって生まれているかと考えると、僕は「文章の読み直しの回数」ではないかと考えています。
具体的には、文章を早く読める人は、一度読んだだけで文章の意味が理解できるため、止まることなく文章が読める、結果的に速く読める。
一方で、文章を読むのに時間がかかってしまう人は、文章を一度読んだだけでは意味が理解できず、何度の読み直しをする必要があるため、結果的に文章を読むのに時間がかかる、ということです。
現に、僕がTOEFLのリーディングで時間がなくなってしまうパターンは、圧倒的にこの後者のパターンです。
また、僕は速読の訓練は一切せず、精読の練習を徹底的に行なった結果、TOEICのリーディングで15分時間を余らせて満点を取得することができました。(もちろんTOEIC用の対策もしました)
何が言いたいかと言うと、精読ができれば、正答率も上がるし、速く読めるし、良いことだらけだよね、ということです。
③ネイティブが書く文章が読める
精読力をつけることによって、ネイティブが書く文章がより高い確率で理解できるようになります。
基本的に、英語の文章というのは、「単語」が「文法」というルールに従って並んでいるため、これら2つが理解できていれば、全ての文章は問題なく読めるはずです。
しかし、これら2つが分かっていても読めない文章というものがあります。それが「ネイティブが書く文章」です。特にインフォーマルな形で書かれた文章ほど読みにくい印象があります。
なぜかというと、インフォーマルな場での彼らの文章は、定形表現(イディオム)を含んでいることに加えて、「省略」や「倒置」といった、基本的な英語の文章の形からあえて逸脱させた形で文章を書くことが多いからです。
例えば、資格試験のリーディングや論文といったフォーマルな場で使用される文章は、きちんと文法のルールに従って、誰が読んでも理解がしやすい明確な形で書かれることがほとんどです。
一方、YouTubeのコメント欄や、現地の人向けの雑誌・インターネットの記事に使用される英語は、先に言ったような「省略」、「倒置」やイディオムが多く含まれているため、非ネイティブの僕らにとって、非常に理解が難しくなります。
しかし、精読力を鍛えて「省略」や「倒置」といった高度な文章表現の読み方に慣れることで、これらのインフォーマルな英語がより理解しやすくなります。
精読の具体的なやり方
それでは、本題の「精読力の鍛え方」を説明します。
なお今から説明する方法は、「基礎的な単語力」と「文法知識」があることを前提に話を進めています。これらの知識、理解に自篠のない方は、まずこれらの基礎を学習した上で勉強に望まれることをおすすめします。
全体の流れ
先に結論から言うと、精読の練習は次の流れで行います。
② 文章の意味を理解する
③ 自分の理解が正しいか日本語訳・解説を読んで確かめる
④ 間違っていた場合は原因を突き止め学習する
⑤ ①~④を繰り返す
そして、文章の意味が理解でき、「なぜその意味になるのか」を他者に説明できるまで、深く理解した時点で次の文章に移ってください。
また、③を見ていただければ分かるように、精読の練習をする際は、必ず日本語訳と一つ一つの文章に対する文法的な説明が詳しく書かれている参考書を使用してください。(おすすめの参考書は記事の後ほど紹介します)
なぜなら、これらの説明がないと「なぜ自分の解釈が間違っており、その原因は何だったのか」を確かめることができないからです。
言い換えれば、間違った解釈をしてしまう原因を知り、正しい解釈にたどり着くまでの思考の過程を学ぶ、ということが精読の練習をする、ということです。したがって、ただ日本語訳が掲載されている文章を読んでも、「どうしてその日本語訳の意味にたどり着くのか」という過程を学習することができなければ、精読力は上がりません。
ここまでの内容はただ言葉で説明をされてもイメージがつきにくいと思うので、実際の文章を例にとってより具体的に説明します。
例題
それでは、次の英文の意味を考えてみましょう。
この文章の意味を、自信を持って正確に理解できたでしょうか?
意味が分かったという方も、よく理解できなかったという方もまずは、自分の頭の中でこの文章の日本語訳を作ってみましょう。
日本語訳ができたら、その日本語訳が正しい日本語訳になっているかどうかを確かめます。
解答・解説
上の文章の正しい日本語訳は以下になります。
この本は参考にはなるけれども(情報量が豊富であるけれども)、理解するのが難しい。
どうでしたでしょうか?、自分の作成した日本語訳と同じ意味になりましたか?
仮にここで自分の作成した日本語訳と、正解の日本語訳が同じ意味になったとしても、まだ終わりではありません。
最初に説明した「精読」の定義に戻ると、精読とは、「その文章が「なぜそのような意味を読者に伝達するのか」を、他者に説明できる状態まで、深く文章を理解する行為のこと。」でした。
つまりこの後、この文章が「なぜ正解の日本語訳の意味にたどり着くのか」を考えるプロセスが必要です。
今回の例文でポイントになるのは、従属節の “Though informative” の部分だと思います。まず原則として “Though” という単語は「接続詞」であり、接続詞の後には “S + V” 、すなわち主語と述語が並ぶはずです。
しかし、今回の例文を見ると “Though informative” とあるように、”Though” の後に「主語」も「動詞」もありません。つまりここで、今回の文章は “Though” の後に “S”と “V” が省略されているパターンの文章である、ということを理解する必要があります。
そして、次に考えることは「この省略された “S” と “V” の部分には一体何が入るのか?」ということです。
結論から言うと、”Though informative” の部分には “Though (this book is) informative” の()の部分が省略されています。
このように、従属節の「主語」と「動詞」が省略される場合、本文と全く無関係の「主語」と「述語」が省略されることは(一部の慣用表現を除いて)起こり得ないため、 “Though” の後ろには、主節と同じ「主語」と「動詞」、すなわち、”this book” と “is” が省略されていると予想されます。
その予想のもと “this book” と “is” を補って英文を読んでみると、「この本は参考にはなるけれども(情報量が豊富であるけれども)、理解するのが難しい。」という意味が読み取れるため、正しい文章の解釈にたどり着く、という流れです。(仮にここで予想した「主語」と「動詞」を補った文章の意味が不自然な場合は、別の可能性を探っていく(例:副詞節の可能性を疑う、慣用表現を疑う)という流れで文章の読解を進めます)
以上が、精読の具体的な練習方法になります。この練習を何度も何度も繰り返し、「なんとなく読める」という状態から「正しく自信を持って読める」という状態に仕上げていくことが、まさに精読力を鍛える、ということを意味します。
精読の練習におすすめの教材2選
それでは、最後に精読の練習におすすめの教材を2つ紹介します。どちらの教材も僕が実際に使用しているものですので、内容が素晴らしいことは保証します。
実際に僕は、これらの本を資格試験のリーディングの勉強を開始する前に必ず学習することで、自信を持ってリーディングの勉強に臨むことができました。
英文読解の透視図
結論から言うと、非常におすすめできます。僕にとっては、この本のおかげで精読力がついたといっても過言ではないです。
中身は「(テクニックなどは無視して)英文の文法構造を理解する力を徹底的に鍛える」というテーマで、各大学の入試問題を利用して精読力を鍛える内容になります。
実際に僕も愛用しており、一つ一つの英文を、これでもかというくらい深く掘り下げて解説してくれるため、とても勉強になります。Amazonでの評価が高いのも納得です。
僕は、精読の練習をするために、たくさんの本を買うよりも、この本を一冊読んで隅から隅まで理解することが有効だと思います。
特に、「単語も文法も分かるけど、文章が読めないことがある」という方におすすめできます。「英語の文章を読んで理解する」とは、どういうことなのかを教えてくれる貴重な一冊です。

ポレポレ英文読解プロセス50
こちらの本も、英文読解の参考書としてかなり有名な本だと思います。
内容は先に紹介した「英文読解の透視図」とほぼ同じで、各大学の入試英語問題を利用して精読力(英文の構造理解力)を鍛える、目的で作られています。
こちらの本も解説がとても丁寧書かれており、かなり勉強になりました。
正直、先に紹介した英文読解の透視図と甲乙つけがたいので、気になる方は両方のAmazonレビューを見て判断されると良いと思います。僕はどちらを選んでも良いと思います。

まとめ
以上、「精読力とは何か?」から「精読力の具体的な鍛え方」、「おすすめの参考書」の紹介をしました。
精読の力を一夜づけでなんとかなるものではなく、参考書を使って、学習を積み重ねることで徐々に英文を読むための思考回路が形成されると思います。
したがって、これから正しく自信を持って英文を読めるようになりたい、という方は、なるべく早い段階で精読の訓練をしてくおくことをおすすめします。
今回の記事の内容が少しでも参考になれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
Twitter(@T_Inagaki_GC)でも「英語学習に役立つ情報」を発信していますので、一度見に来ていただけると幸いです。

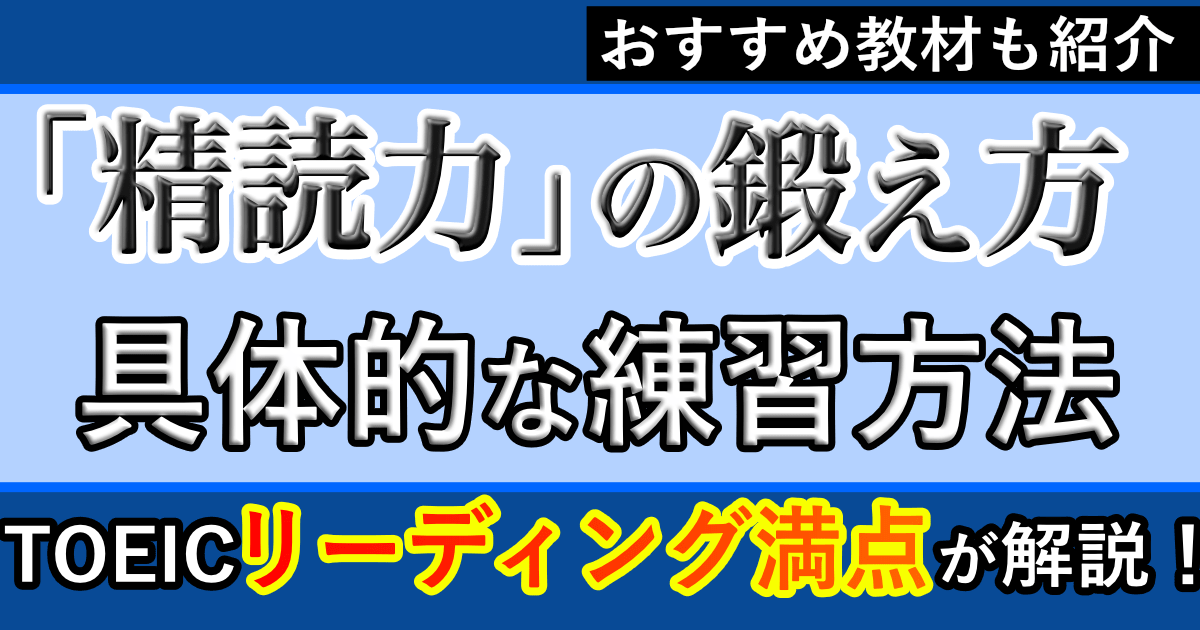
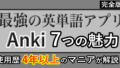

コメント