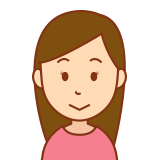
TOEFLのリーディングで高得点を取りたいけど
- どうやって勉強したら良いんだろう?
- どういう教材を使ったら良いのだろう?
- 高得点を取るコツがあるのだろうか?
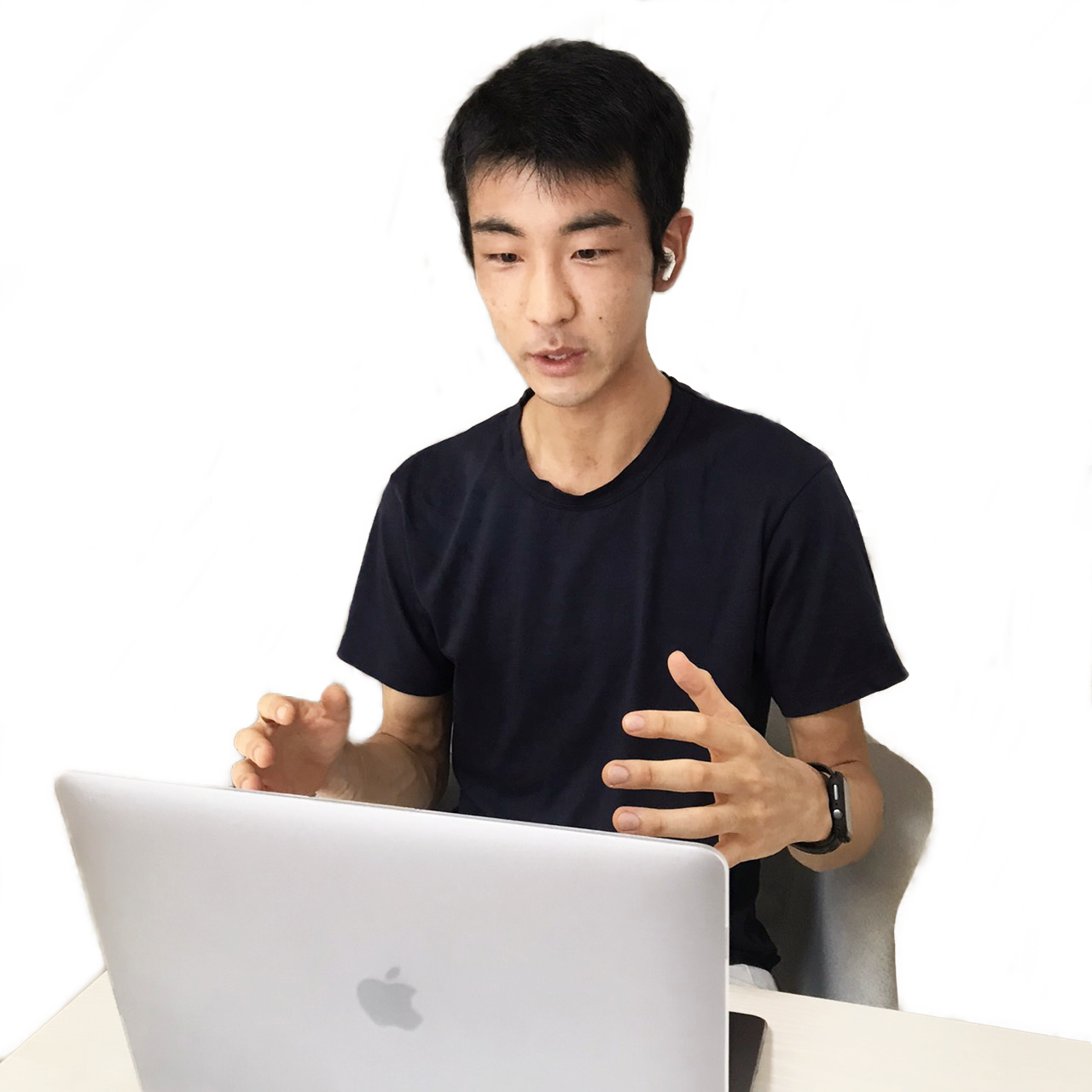
このブログを運営しています稲垣達也(@T_Inagaki_GC)と言います。
僕は独学でTOEFLリーディングセクションで満点を取得することができました。
本記事を最後まで読んで頂くことで、これらの疑問を解消します。
本記事では、僕がTOEFLリーディングで満点を取るために行った対策を、具体的に紹介しています。
僕と同じように、国内でTOEFLの対策をしている方の役に立てれば嬉しく思います。
TOEFLリーディング問題の概要
まず、TOEFLリーディングセクションの問題形式を確認します。
テストの構成
問題の特徴は以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 問題数 | 3~4パッセージ |
| 設問数 | 10問 |
| パッセージの語数 | 約700語 |
| 制限時間(1題) | 18分 |
| トピック | 自然科学、社会科学、芸術などの幅広い分野の教養科目 |
問題の種類
次にTOEFLのリーディングで出題される問題の種類を確認します。
| 種類 | 問われる内容 | 例 |
|---|---|---|
| 正誤 | 本文の内容との正誤 | Which of the following is true about ~? |
| 推測 | 本文の内容から推測されること | What can be inferred from the paragraph 2? |
| 意図 | 著者の意図 | The author mentions ~ in paragraph 4 in order to |
| 語彙 | 単語・表現の意味 | The word ~ in paragraph 3 is closest in meaning to |
| 指示語 | 代名詞・関係代名詞に該当する語・表現 | The word which in paragraph 5 refers to |
| 言い換え | 特定の文章の意味を言い変えた文章 | Which of the sentence best expresses the essential information in highlighted sentence in paragraph 1? |
| 挿入 | 与えられた文の挿入位置 | Where would the sentence best fit? |
| 要約 | 本文を要約した文 | Complete the summary by selecting the best THREE answer choices that express the main ideas of the passage. |
その他のTOEFLリーディングに関する情報を以下にまとめておきます。
・回答形式は4択から1つ選択肢を選択する形式が基本、その他は要約問題の3つの選択肢を選ぶパターンと、選択肢の文を2種類に分類するタイプの問題も出題
TOEFLリーディングの勉強法
ここでは、TOEFLリーディングセクションで高得点を取るための勉強方法を、5つのステップに分けて解説します。
【STEP 0】前準備
TOEFLのリーディングで実際に問題を解き始める前に、「TOEFLの頻出単語」と「精読」の習得は必須です。
なぜなら、これらの知識がない状態で問題演習を行っても、おそらく問題は解けないため、復習に時間がかかりすぎてしまい、効率的に学習が進まない可能性が高いからです。
問題演習をする目的は、問題を解くことによる「新しい知識の習得」に加えて、「問題を解くことになれる」という2つです。
後者の「問題を解くことになれる」というのは、すなわち「持っている知識をいかにして使うか」という訓練のことを意味します。
前提知識がない状態で「持っている知識をいかに使うか」という練習を行うことは難しいため、問題演習によって得られる学びが少なくなります。
そのため、これら2つの習熟度に自信のない方は、まずは前提知識の定着から取り組まれることをおすすめします。(「単語の覚え方」、「精読の練習方法」は後日、別記事で解説する予定です)
【STEP 1】問題を解く
前提知識の習得が完了したら、手元の問題集を使って問題を解きましょう。
問題は復習がしやすいように、1セット(10問ずつ)18分の時間を測って解くことをおすすめします。
もちろん試験日が近づいて、本番と同じ形式で解きたい場合は、3セット54分を測って解いても良いと思います。
問題を解く際は、できればPCを使って本番と近い環境で解くことをおすすめします。普段からPCで英語の文章を読むことに慣れておいた方が、本番に変な違和感を感じなくて済むからです。(もちろん紙の本しかない場合は、そちらを使って勉強しても構いません)
【STEP 2】解答を確認する
問題を解き終わったら解答を確認します。
その際、正答率に応じて、次の通りのステップに進みます。
- 間違えた問題がある場合→【STEP 3】間違えた原因を特定する
- 全問正解した場合→【STEP 4】全文を読み直す
【STEP 3】間違えた原因を特定→対処
間違えた問題がある場合は、その間違えたが生じた原因を特定します。
TOEFLのリーディングセクションで間違えが生じるパターンは、以下のパターンに分類できると思います。
パターン① 文章の意味が分からなかった
本文、問題文を含めて文章の意味が分からなかったため、間違えてしまったパターンです。
さらに細分化すると、以下の2つのパターンに分類できます。
それぞれの対処法は以下の通りです。
→知らなかった単語・表現をAnkiに単語登録し、翌日以降に復習する
(詳しい方法は別記事で解説予定)
②文法的に意味が分からなかった(例:省略、倒置が原因で意味が取れなかった)
→精読力を高める
(詳しい方法は別記事で解説予定)
パターン② 解く時間が足りなかった
ある問題を解くために時間を使いすぎてしまい、他の問題を解くための時間が足りなかったというパターンです。
解く時間が足りなくなってしまう原因を、さらに詳しく分析すると、本文または問題文の特定の文章の意味が1度読んだだけでは分からなかったという事が多いです。
よく「文章を読むスピードが遅い」=「速読力が足りない」と思われる方が多いですが、個人的にはこの表現は正確でないと思います。
僕は 「文章を読むスピードが遅い」=「文章の意味を1度読むだけで理解する力が足りない」、すなわち「精読力」が足りないことが原因だと思います。
この主張の根拠として、僕は文章を1行ずつ丁寧に読み進めることで、TOEFLのリーディングはほぼ全て時間内に解き終えています。
つまり、「問題を解く時間が足りなかった」という原因の対処法は、「精読力」を上げることです。精読力が上がれば、(問題演習を重ねるにつれて)自然と文章を読むスピードも速くなります。
「じゃあ、精読力ってどうやってあげればいいねん」って思った方は、後日、別記事で「精読力を高める方法」を詳しく解説予定ですので、そちらをご覧ください。
パターン③ ケアレスミス
単純に自分の不注意によるミスです。
特に、「~ではないものを選びなさい」という問題でよくやりがちだと思います。(僕はこのタイプの問題で、よく間違えていました)
対処法はとてもシンプルで、「問題文をしっかり読むくせをつける」ことです。
TOEFLのリーディングで、本文はとても丁寧に読むが、問題文はさらっと流し読みする、ということをやってしまいがちですが、問題文ほど丁寧に読み込む、という意識を日頃の練習からつけましょう。
【STEP 4】全文を読み直す
以上のステップが完了したら、仕上げに全文を読み直しましょう。
この作業の目的は、正解はできたが(もしくは問題に関係ない部分で)意味が取れなかった文章を洗い出すためです。
対処法は以下の通りです。
→知らなかった単語・表現をAnkiに単語登録し、翌日以降に復習する
(詳しい方法は別記事で解説予定)
②文法的に意味が分からない文章が見つかった(例:省略、倒置が原因で意味が取れなかった)
→精読力を高める
(詳しい方法は別記事で解説予定)
【問題別】正答率を上げるためのコツ
ここでは、問題の種類別に正答率をあげるための、ちょっとした「コツ」や「考え方」を紹介します。
大前提
まず、コツを紹介する前に、TOEFLリーディングで点数を上げるためには、圧倒的に「精読力」が重要であるということを確認しておきます。(イメージ:精読力95%、コツ5%)
正答率を上げるための「コツ」や「考え方」は、あくまでも補助的な役割であることを意識しましょう。(極端な話、精読力が圧倒的に高いネイティブは、これらのコツなど使わなくても満点が取れると思います)
かと言って、全く重要で役に立たないかと言ったらそうでもないので、僕の独断と偏見で、正答率を上げるための「コツ」や「考え方」 を紹介します。ご参考までに。
今回は、よく間違えてしまうタイプの問題に焦点を絞って紹介します。
文挿入問題
与えられた文章を、本文の空欄4箇所のうち、どこに挿入するかを選択する問題です。
この問題を解くコツは、「代名詞の意味に注目する」です。
代名詞とは、日本語で言う「これ」「あれ」「それ」のような単語です。
英語における代名詞は、”it”:何か特定の単語、”this”:特定の文章、節をそれぞれ指します。この代名詞の意味を軸に文章を挿入する箇所を決める、ということです。
具体的には、以下のようなイメージです。
・「挿入する文章」に代名詞が含まれている場合
例えば、”This shift ~.”という文章挿入する場合、直前の文章には必ず何かの変化、変遷に関する記述がある
・「本文」に代名詞が含まれている場合
例えば、”It grew ~.”という文書が挿入箇所の直後にある場合、挿入した文章の何が”it”に当たるのか、仮にそれが”it”だとして文章として成立するか?を判断基準に選択肢を選ぶ
言い換え問題
本文でハイライトされた文章と、同じ意味を表現している文章を選択する問題です。
この問題を解くコツは、「間違った選択肢のパターンを頭に入れておく」ことです。
(僕が勝手に分類した)間違った選択肢のパターンは下記の通りです。
パターン① 違う意味の事を言っている
間違った選択肢の中で、一番分かりやすいパターンです。
これは、選択肢の文章の意味が取れれば、簡単に消去できるため、解くためのコツはありません。
パターン② (ハイライトされた文章の)情報が網羅しきれていない
選択肢の文章と、ハイライトされた文章の言っていることは合っているが、ハイライトされた情報の一部が抜け落ちているパターンです。
これは、個人的に最も間違えやすいパターンです。
対処法はシンプルで「あ、これあってるじゃん」と、反射的に選ばないように注意することです。
選択肢を消去する際の判断基準として「内容の正確性」に加えて、「情報の網羅性」という視点も持っておいたほうが良いと思います。
パターン③ 原因→結果の順序が逆
これは、ハイライトされた文章と主張していることは同じだが、論理の関係が間違っているパターンです。
これも間違えやすいため、注意が必要です。
個人的には「これどっちの選択肢もあってるじゃん」と思ったときに、片方がこのパターンであることが多い印象です。
選択肢を消去するかどうかを判断する際は、主張している内容(結果)に加えて、その結果が導かれるまでの「因果関係が合っているか」にも注意しましょう。
要約問題
TOEFLリーディングの最後に出現する、本文の内容を要約した文章を選択する問題です。
この問題に関しても対処法は、 「間違った選択肢のパターンを頭に入れておく」ことです。
(僕が勝手に分類した)間違った選択肢のパターンは下記の通りです。
パターン① 違う意味のことを言っている
選択肢の文章が本文とは違う内容のことを言っているパターンです。例えば、本文と逆の内容、無関係の内容、誇張が含まれている内容が選択肢として出てくることがあります。
これは、1番分かりやすいパターンであるため、文章の意味が取れれば簡単に消去できると思います。
パターン② 網羅性が低い(内容が具体的すぎる)
選択肢の文章の内容が網羅性が低く、本文の具体的な内容のみを表している場合です。
基本的に、本文の要約した文章を選ぶ問題では、パラグラフの内容を網羅的にかつ端的に表した文章が正解であることが多いと思います。
つまり、選択肢の文章がパラグラフの具体例だけに言及している場合、もしくはパラグラフの伝えたい内容にそれほど大きな意味を持たない選択肢は間違っていることが多いと言えます。
個人的な感覚として、ふわっとパラグラフの内容と大きくハズレていない内容を表している選択肢は合っていることが多く感じます。(抽象的で申し訳ありません)
また、文章の長さは正解・不正解に関係ないことが多いです。
高得点をとるためのテクニック4選
ここでは、TOEFLリーディングセクションで高得点を取るためのテクニックを4つ紹介します。
【テクニック①】自宅受験を選択する
これはテクニックとは違うかもしれないですが、TOEFLは、自宅受験を選択することをおすすめします。
詳しい理由は後日、別記事で紹介予定ですのでそちらをご覧ください。
【テクニック②】1度解いた問題は2度解かない
TOEFLリーディングの問題を解くときは、1度解いた問題は2度目を解く必要はないと思います。
これは、1度解いた際に丁寧に復習をしていれば、2度目を解くことで得られる学びが少なくなってしまうためです。
加えて、1度解いた問題は、ある程度先の展開が分かってしまうため、完全に初見の問題が出てくる本番の練習にも、ならない可能性が高いです。
それと同時に、本番で初見の問題に対峙したときに感じる、強烈なプレッシャーも感じられなくなってしまうため、本番でいつも通りの力を発揮するための練習も積むことができなくなります。
【テクニック③】消去法で解く
TOEFLリーディングの問題は、語彙問題を除いて、基本的に「消去法で解く」ことをおすすめします。
なぜなら、「正解である選択肢を選ぶ」ことより「間違っている選択肢を消去する」ことの方が簡単であることが多いからです。
これは言い換えると、正解である理由を探すのは難しいが、間違っている理由を探すのは簡単ということになります。
TOEFLの問題を作る側も、間違った選択肢を作るときには、どこが間違っているかを必ず意識していると思います。(回答者から問題の誤りを指摘されないために)
したがって、正解そうな選択肢を見つけても、必ず他の全ての選択肢に目を通し、間違っている理由を見つけておくと、高い確率で正解の選択肢が選べるようになります。
また、こうすることで、自信を持って正解を選べるため、「次の問題に集中できる」という副次的なメリットもあります。
【テクニック④】問題文に先に目を通す
問題を解く際は、「問題文を読む」→「該当箇所が含まれている本文を読む」→「問題を解く」の流れで進めていくことをおすすめします。
なぜなら、文章を読みながら答えを探すことで、時間の短縮(読み直しの回数削減)、正答率の向上が見込めるからです。
よく問題を解く前に「本文を最初から最後まで読み通したほうが良い」というアドバイスを聞きますが、個人的には必要ないかなと感じます。
これに関係して、よく耳にする「飛ばし読み(文章の意味をなんとなく分かった状態でどんどん読み進める読み方)」もやめた方が良いと思います。
何度も言いますが、正答率を上げる一番の近道は徹底的な「精読」です。
TOEFLリーディングにおすすめの教材
ここでは、TOEFLリーディングで高得点を取るために使用できる、おすすめの教材を紹介します。
こちらで紹介する教材は全て僕が実際に使ったものです。他の市販の教材を全て使い、比較して評価しているわけではないので、そのことを踏まえた上で、参考程度に読んでいただければと思います。
単語帳
まずは、TOEFLリーディング対策で、僕が実際に使用した単語帳を紹介します。
TOEFLテスト英単語3800 4訂版(音声DL付)
TOEFLの勉強をしたことがある方なら、一度は目にしたことはあるくらい有名な単語帳です。
僕は、書籍版ではなく「POLYGLOTS」というアプリを使って、この単語帳を購入し学習しました。(現在は旺文社から公式のアプリがでているようなので、そちらを使っても良いと思います)
これはTOEFLに限った話ではなく、単語を学習するときは、書籍ではなくアプリを使うことをおすすめします。
理由は以下のとおりです。
・復習の管理が楽(間違った問題をマークできる)
・単語の勉強に対する、心理的なハードルを下げることができる

問題集(日本語の解説が必要な場合)
次に、TOEFLのリーディング対策でおすすめの問題集を紹介します。ここでは、日本語の解説が必要な場合と、必要でない場合とで、分けて紹介します。
TOEFLのリーディングの勉強をこれから始める、という方はとりあえず、日本語の解説がついたものを買っておくことをおすすめします。
TOEFLのリーディングで高得点をとる自信があり、あとは問題になれるだけ、という方は日本語の解説がついてない(英語の解説のみ)の教材を使うことをおすすめします。
極めろ!TOEFL iBTテスト
リスニングの勉強方法を解説した記事でも紹介した本です。
英語講師として有名な森田鉄矢先生、TOEFL117点の日永田伸一郎先生、そしてTOEFL満点の山内勇樹先生の豪華メンバーが監修しています。
個人的にはTOEFLリーディング対策の問題集として、「最初の1冊」に適した教材だと思います。
以下、この教材の良い点と残念な点です。
・問題の質が高い(本番の問題とほぼ同じ難易度)
・PCを使って、本番と同じような環境で問題演習が可能
・2019年8月からの新形式に対応

TOEFL iBT® TEST リーディングのエッセンス
Z会編集部が監修しているTOEFLリーディングの問題集です。
問題数も多く、かつ問題の質も高いため、個人的にかなり好印象です。1回目のTOEFLiBTのリーディングで満点を取ることができたのは、この教材のおかげだと思います。
以下、この教材の良い点と残念な点です。
・問題の質が高い(本番の問題とほぼ同じ難易度)
・PCでの問題演習が不可

問題集(日本語の解説が必要ない場合)
次に、日本語の解説が必要ない場合におすすめの問題演習用プラットフォーム(Webサイト)を2つ紹介します。
KMF
中国のWebサイトです。無料でTOEFL公式の模試を50回分解くことができる革命的なWebサイトです。
TOEFLのリーディングはPC画面上の問題を読む練習をしたほうが良いため、このWebサイトを活用して本番と近い環境が再現できることも素晴らしいポイントです。
良い点
- 無料
- 模試が50回分解き放題
- 問題の質が高い(TOEFL公式の問題を解くことができる)
- 本番とほぼ同じ環境で練習できる
残念な点
- 初期設定がやや面倒(別記事で詳しく解説予定です)
- 言語が中国語(GoogleのWebサイトごと翻訳する拡張機能を使えば、問題なく使えます)
BestMyTest
カナダのバンクーバーにある”Zebra Education Inc”という企業が運営している、TOEFL受験者用のオンライン練習プラットフォームです。
良い点
- 問題数が多い
- 本番と同じような環境で練習可能
- 問題の質も十分高い
残念な点
- 料金がやや高い(1ヶ月で7,400円)
まとめ
今回はテクニック的な部分を説明しましたが、TOEFLのリーディングで高得点を取るためには、精読の力が圧倒的に重要です。(最後に念を押して)
精読の練習方法の具体的な方法は、後日別の記事で解説する予定です。そちらをぜひご覧ください。
本記事を読むことで、TOEFLリーディングの勉強法のヒントを得ていただければ嬉しく思います。
Twitter(@T_Inagaki_GC)でも「英語学習に役立つ情報」を発信していますので、一度見に来ていただけると幸いです。


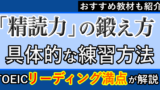



コメント